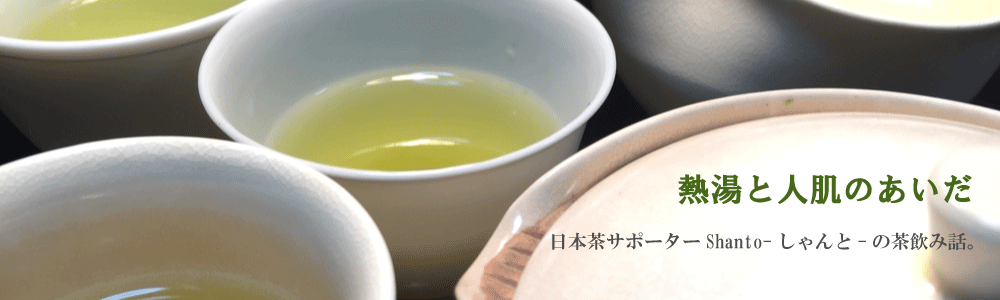つい先日のことであるが、煎茶が切れたので購入せんければいかんと思いつつも
ウチの近所には気に入った茶舗は少なく、通販にするか京都に買いに出掛けるかと
思案した結果、京都に行く時間は無く、通販で購入しても2日は掛かるのであって、
どうも我慢が出来そうにない。
近所で「一番まとも」と云ったら御幣があるかもしれないが、その茶舗に行って
適当な煎茶をセレクトすればええかいなとも考えたが、どうも自分の中で納得が
いかない。
「何故に納得がいかない」のかは判然としないが、あまり好みでない煎茶に
「ええ値段」を支払いたくなかったし「適当な煎茶をセレクト」というワードが頭脳に
浮かんだことこそがどうも禍々しい。
他に淹れるお茶がない訳ではないのだから、ここは我慢と思いつつ悶々とした
心持ちで食材の買出しへ。
イ○ン・グループの所謂「スーパーマーケット」は近所に数多くあり、駐車場も完備
されているので自分は頻繁に利用する。
本当はウチから徒歩一分の「スーパー」で買い物すればいいのだけれども、ここの
従業員の客をナメた態度とレジ係りのパートのお姉さん方の茶髪率の高さ&死んだ
魚のような視線、或いは態度に自分の純情な感情は空回りして耐えることが出来ず
買い物に行く度に悔しい思いをして嗚咽が止まらない様なことがしばしばあり、嫌い
なのでわざわざ車でイ○ンまで買出しに行くのであって「ここはアメリカか……」
なんて思いつつも仕様がない。
そんなことはどうでもいいのだが、このイ○ン・グループのスーパーで
「一番摘みやぶきた煎茶」というのを発見した。
プレミアム・トップ・ヴァリューセレクトらしいこの煎茶のパッケージには
「日照時間が長く温暖な気候の鹿児島県南部のお茶です。うまみとコクあるやぶきた種の
一番茶を使用しました。甘みのある濃厚な渋みと香りが特徴です」とおもいっきり書かれている。
値段もそこそこええ値段であり100gで800円弱、ここで頭脳の天使が「購入するのは
やめなさい」と囁いたかと思いきや今度は「ユー買っちゃいなよ、我慢できねーんだろ」
なんてドS口調で悪魔が囁くもんだから抗いようもなく、買い物籠にその煎茶はスルスル
と沈んだ。
「煎茶飢餓状態」で帰宅。
早速、淹れるべくパッケージを開封するや否や驚いたのは甘くて香ばしい香り、
これはどこかで嗅いだことのある「茶」の香りである。
これまた驚いたのは茶葉も想像していた「ピンとした」ものではなく限りなく
「粉茶」に近いものであり、粉茶の中に良い茶葉が点在している状態であって
プレミアム感は無いに等しいが香りは良いと感じた。
「おいおいプレミアム・トップヴァリューセレクト!」と叫んだ声は往来にまで到達
していたに相違ないが、そんなことは気にせず自分はあうあうした。
あうあうしつつも「一番摘みやぶきた煎茶」を淹れてみる。
粉状の茶葉なので量に注意しつつ、冷ました湯を急須に注ぎ待つこと一分、
茶碗に注いで見ると黄色が少し強めの水色、香ばしく甘い香気と味、これは
所謂ところの「深蒸し煎茶」ではないか。
「一番摘みやぶきた深蒸し煎茶」ならば納得もするが「一番摘みやぶきた煎茶」
としてこれは販売されている。もやもやする。
しかし、さすが温暖で日照時間が長く肥沃な土地で育った鹿児島のお茶だけあって
美味しいのであるが、なんとなく腑に落ちないというか「もやもや感」だけが残って
またあうあうした。
ここからは単なる個人的な意見であるが、この「一番摘みやぶきた煎茶」は良い茶葉
を使用していると思われるが「茶がよく出る」ように深蒸しにしたことによって茶葉が
粉状になった或いは「粉状にした」のか、もっと穿ったものの見方をすれば、良い茶葉
の製造過程で残った「粉茶」に良い茶葉を心持ちブレンドして提供してるんちゃうんのん
とも受け取れるというか思ってしまうのが尋常なる消費者の気持ちではなかろうか。
そこまで考えへんか。
ぐだぐだと書したけれども、よくよく考えるに100g800円の茶葉をスーパーで購入する
ことに対して感じたことは「もったいないなぁ」ということ。
スーパーで売っているお茶が悪い訳ではない。
スーパーでお茶を買うのは手軽であるし悪いことではないが、売られているお茶の
情報というのはパッケージの説明だけである。
これが「茶舗」ならどうであろうか。
「100gで800円の煎茶ならこんなどうでしょう?」なんてその場で淹れてくれたりして
味と香りを確かめて購入することが出来るし、そのお茶の美味しい淹れかた、生産地
なども事細かに教えてくれるであろう。
これが本当の「プレミアム」なのではないだろうか!
「茶舗で茶葉を購入する」という至極当然なことが非常に肝要なのだと改めて
気付かされる経験であった。
やはり時間が無くとも京都、或いは宇治に出向いてお気に入りの茶舗で茶葉を
購入したいものである。
「茶舗にて茶葉を購入することの楽しさ」についてはまた別の機会に触れたいと
思うが、一体全体この長々とした駄文を誰が読むのだろうかと考えつつあうあうして
筆を置きたい。